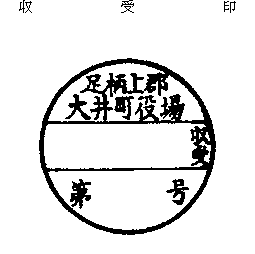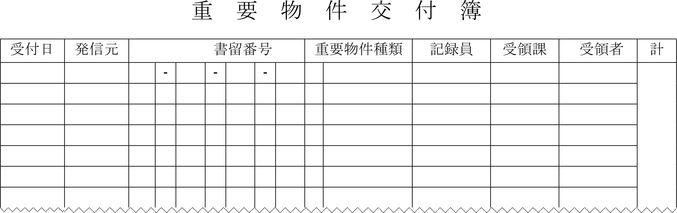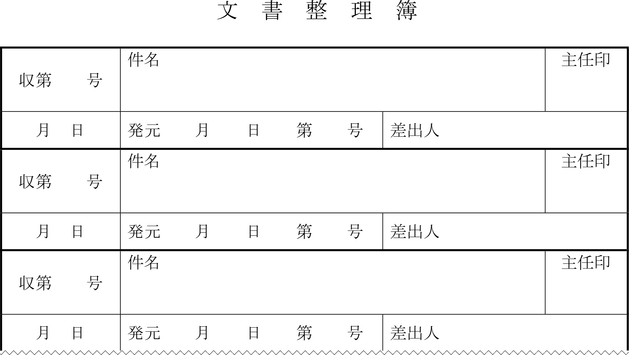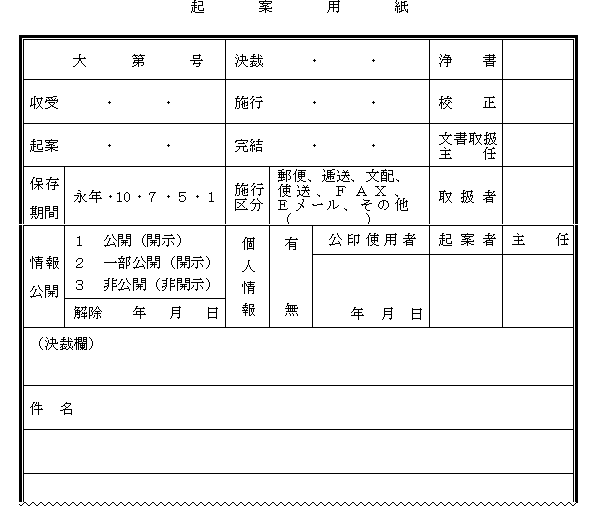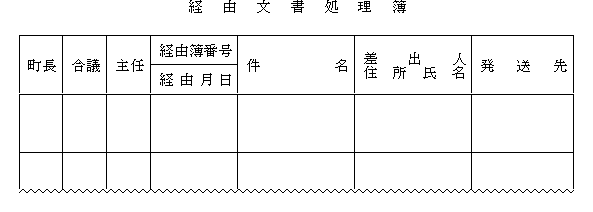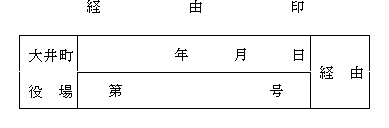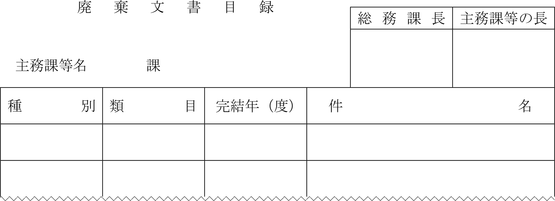○大井町文書取扱規程
昭和40年5月1日訓令第20号
大井町文書取扱規程
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 文書収受及び配布(第5条―第13条)
第3章 文書の処理(第14条―第27条)
第4章 文書の浄書及び発送(第28条―第34条)
第5章 文書の整理及び保存(第35条―第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除き、大井町における文書の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(課等の長の職務)
第2条 課等の長は、その課等における文書事務が適正かつ円滑に処理されるように努めなければならない。
(文書取扱責任者の設置等)
第3条 課等の長の文書事務の処理を補佐するため、課等の長の指名により文書取扱責任者を置く。
2 文書取扱責任者は、上司の命を受け、次の各号に掲げる事務に従事する。
(1) 文書の処理の促進に関すること。
(2) 文書の審査に関すること。
(3) 文書事務の指導及び改善に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関し必要なこと。
(文書事務の指導及び改善)
第4条 総務課長は、各課等の文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう指導及び改善に努めなければならない。
第2章 文書収受及び配布
(一般的取扱い)
第5条 大井町に到達した文書は総務課長が収受し、開封しないと主務課の分からないものは開封し、それ以外のものはそのまま課等の長に配布しなければならない。
(特殊扱い)
第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書は総務課長が収受し、それぞれ当該各号に定める手続により配布しなければならない。
(1) 普通文書中、重要又は異例にわたると認められるものは、課等の長に配布する前に副町長及び町長の閲覧を受けるものとする。
(到達時刻の記載)
第7条 審査請求書到達の日時がその行為の効力又は権利の得失若しくは変更に関係のある文書は、前2条の規定により取り扱うほか、その文書の余白に取扱者が到達時刻を朱書し、押印しなければならない。
(文書収受の特例)
第8条 定例又は軽易な案件で一時に大量の処理を要する文書は第5条又は第6条の規定にかかわらず、あらかじめ総務課長の承認を得て、直接課等の長が収受することができる。
(郵便料金未納等の文書の処理)
第9条 郵便料金の未納又は不足の郵便物は、総務課長が必要と認めるものに限り、その未納又は不足の料金を支払って収受することができる。
(勤務時間外に到達した文書の取扱い)
第10条 勤務時間外に到達した文書は、当直員が受領し、総務課長に引き継ぐものとする。
(文書の配布)
第11条 文書は総務課員によって主務課等へ配布しなければならない。
2 数課に関係のある文書は総務課長が、その文書の処理に最も関係の深いと認める課等に配布しなければならない。
(課等内での配布)
第12条 課等の長は配布を受けた文書を査閲し、処理の方針を定めて文書取扱責任者に配布しなければならない。
2 文書取扱責任者は文書の配布を受けたときは、直ちにこれを閲了し、文書整理簿(第3号様式)に搭載し、自から処理するものを除くほか、処理の方針を示して主任者に配布しなければならない。
第3章 文書の処理
(配布文書の処理)
第13条 主任者は、文書の配布を受けたときは、速やかに、その文書を処理しなければならない。
2 主任者は、あらかじめ上司の指示を受けて処理することが適当であると認める文書は、その文書の余白に「一応供覧」と朱書し、上司の指示を受けなければならない。
3 主任者は、単に受理に止まる文書は、その文書の余白は「供覧」と朱書し、上司の閲覧を受けなければならない。
(起案)
第14条 起案は原則として文書によるものとし、起案用紙(第4号様式)を用いなければならない。ただし、定例又は軽易な文書は、収受した文書の余白に処理案を記入し、処理することができる。
(起案の要領)
第15条 起案は、次の各号に掲げる要領によるものとする。
(1) 文書の書式及び文章については、大井町公用文に関する規程(平成6年大井町訓令第1号)に定めるところによるものとする。
(2) 電報案は、特に簡易に書き、電文を傍書し、終りに総字数を記入すること。
(3) 金額その他重要な箇所を訂正したときは、その箇所に押印すること。
(4) 起案の理由その他参考となる事項を記入した書面及び関係書類を案文に添付すること。ただし、定例又は軽易なものは、この限りでない。
2 同一文例(以下「例文」という。)によって継続的に起案することのできる事案については、あらかじめ例文を総務課長に合議して定めるとともに、その例文の写を総務課長に送付することにより、個々の起案の際は、例文の記載を省略することができる。
(記号及び番号)
第16条 文書には、次の各号に定めるところにより、記号及び番号を付さなければならない。ただし、軽易な文書には記号及び番号を省略することができる。
(1) 条例、規則、告示及び訓令の記号はその区分により「大井町条例」「大井町規則」、「大井町告示」、「大井町訓令」とし、告示簿の番号とする。
(2) 指令の記号は「大井町指令」の次に、次号に定める一般文書の記号を加え、番号は文書整理簿に記載された収受番号を用いること。
(3) その他の文書の記号は、別表に定める課等の略字を加え、番号は文書整理簿に記載された収受番号を用いること。
(4) 同一事件に属する文書は完結するまで同一の記号及び番号を用いること。ただし、往復の回数に従い順次枝番号を「の2」「の3」のように付さなければならない。
(5) 文書の番号は前号に掲げるものを除き、毎年4月1日をもって更新すること。
(6) 前号の規定にかかわらず、第1号に掲げる文書の番号は、毎年1月1日をもって更新すること。
(7) 異なる番号の収受文書を一つの文書により処理するときは、その番号のうち適宜なものを文書番号として処理すること。この場合においては「合併」の表示とともに他の番号を起案した文書(以下「回議書」という。)の特別扱欄に朱書すること。
(日付)
第17条 文書の日付は施行の日を用いるものとする。
(特別取扱いの表示)
第18条 施行に特別取扱いを必要とする文書は、回議書の所定欄に「至急」「重要」「秘」「親展」「書留」「小包」「電報」「葉書」「例規」「公印省略」等と朱書しなければならない。
(決裁区分の表示)
第19条 回議書には、事務決裁規程の定める決裁区分により、次に掲げる決裁区分を表示しなければならない。
(1) 町長の決裁を要するもの
(2) 副町長限りで決裁するもの
(3) 参事限りで決裁するもの
(4) 課長等限りで決裁するもの
(その他の表示)
第20条 回議書には、記号、番号、収受年月日、編集区分、発送区分等を所定欄に記入しなければならない。
(回議の順序)
第21条 回議書は、順次課長等へ回議した上、町長又は大井町事務決裁規程(平成9年大井町訓令第3号)の規定により専決権限を有する者の決裁を受けるものとする。
(合議)
第22条 回議書は、関係のある課等の長に合議しなければならない。その範囲は必要最小限にとどめるものとする。
2 合議の順序は主務課等の長を経て関係の深い課から順次行うものとする。
3 合議を受けた関係課等の長間に異議があるときは、主務課等の長と協議し、協議が整わないときは、直ちに上司の指示を受けなければならない。
(秘密文書等の取扱い)
第23条 回議書で秘密を要するもの、特に緊急を要するもの、又は特に重要なものは責任者が自ら携行して説明し、決裁及び合議を受けなければならない。
(回議、合議印)
第24条 回議又は合議を受けた事案に異議がないときは、回議書の所定欄に押印又は署名(電子署名を含む。)しなければならない。
(代決及び後閲)
第25条 決裁権者が不在中あらかじめ定められた職員が代決したときは、「代」と朱書きし、押印又は署名するものとする。この場合において、軽易なものを除き、決裁権者の登庁後直ちに閲覧を受け押印又は署名を受けなければならない。
2 前項の規定は、決裁を受けるまでの手続過程において、合議を受ける者等が不在の場合に準用する。
(施行中止又は保留)
第26条 決裁後、新たな事態の発生により施行を取り止め、又は保留しなければならないときは、新たにその旨を起案し、決裁済の回議書(以下「原議」という。)を添付して決裁を受けなければならない。
第4章 文書の浄書及び発送
(浄書)
第27条 文書の浄書は、原則として主務課等において行う。ただし、総務課長が必要と認めるものは、総務課において行う。
(経由文書の処理)
(文書の審査)
第29条 課等の長は、第28条に掲げる文書を決裁するに際し、総務課長の審査を受けなければならない。
2 総務課長は、回議された原議について違法若しくは違式を認め、又は字句の訂正を要するときは、これを訂正してその旨を主務課等の長に通知しなければならない。
(公印の押印)
第30条 浄書した文書は、公印の押印を受けなければならない。ただし、軽易な文書については、公印を省略することができる。
(発送)
第31条 発送する文書物品は、所定の場所に文書物品の発送時刻の1時間前までに総務課に回付しなければならない。ただし、急施を要する文書はこの限りでない。
2 総務課長は、前項の規定により回付された文書物品を郵送、使送等の区分に従い発送しなければならない。
(文書発送後の処理)
第32条 発送済の原議には、取扱者が発送年月日を記入し、押印するとともに文書整理簿の発送年月日欄に、完結したものにあっては完結年月日欄にあわせて記入し押印しなければならない。
第5章 文書の整理及び保存
(文書整理の原則)
第33条 文書は常に整理し、紛失、火災、盗難等の予防を完全にし、重要なものは、非常の際に速やかに持ち出せる等支障のないようあらかじめ準備しておかなければならない。
2 未処理文書は、一定の場所に整理保管し、常に文書の所在を明らかにしておくこと。
3 処理済み文書は、会計年度ごとに整理し、保管するものとする。ただし、暦年ごとに整理し、保管することが適当なものについては、暦年ごとに整理し、保管することができる。
4 前項に規定する会計年度又は暦年の帰属の基準は、文書の処理済み年月日によるものとし、当該処理済み年月日は、告示した文書にあっては告示年月日、その他の施行した文書にあっては施行年月日、単に受理にとどまる文書にあっては供覧年月日によるものとする。ただし、4月1日から5月31日までの間において施行する前年度の出納にかかわる文書にあっては、前年度に帰属するものとする。
5 処理済み文書は、原則として現年度及び前年度にかかわるものを整理し、保管するものとする。ただし、暦年ごとに整理し、保管することが適当なもの及び第39条第2項の規定により主務課等の長が保管する場合は、この限りでない。
(文書の庁外持出し制限)
第34条 文書は庁外に持ち出すことはできない。ただし、主務課長の承認を得たものはこの限りでない。
(処理済み文書の整理及び保管)
第35条 処理済み文書の整理及び保管は、ファイリングキャビネット(以下「キャビネット」という。)に収納することにより行うものとする。ただし、帳簿、台帳、名簿等でキャビネットに収納することが不適当なものについては、この限りでない。
2 前項本文の規定により処理済み文書を整理し、保管しようとするときは、次条第1項に規定するファイル基準表(以下「ファイル基準表」という。)の区分に従い、つづり込みをしないで該当個別フォルダーに収納しなければならない。
3 同一の処理済み文書でファイル基準表の2以上の個別フォルダーに関係があるものは、最も関係の深い個別フォルダーに整理し、保管するものとする。
4 処理済み文書を同一の個別フォルダーに収納しようとするときは、処理済み年月日の古いものから順に置き、最も新しいものが最前に位置するように置かなければならない。
(文書管理システムによる処理)
第36条 この訓令の規定により行うこととされている文書の取扱いに関する事務について、文書管理システムを利用することができる場合は、原則として文書管理システムにより行うものとする。
(保存期間)
第37条 文書の保存期間は、法令で特別の定めのあるもののほか、永年、10年、7年、5年、1年とする。
(文書の種別及び類目)
第38条 文書の種別はおおむね次のとおりとする。
第1種に属する文書
(1) 条例、規則その他例規
(2) 他の官公署及び住民等との往復書類で将来例証となる重要な書類
(3) 町議会議案、報告案、議決書その他町議会に関する重要な書類
(4) 職員の進退及び賞罰に関する書類並びに履歴書
(5) 褒賞及び表彰に関する書類
(6) 争訟に関する書類
(7) 予算及び決算に関する重要な書類
(8) 統計書類及び地図類で特に重要な書類
(9) 町史の資料となる重要な書類
(10) 原簿、台帳等で特に重要な書類
第2種に属する文書
(1) 行政処分に関する書類で永久保存の必要のないもの
(2) 町議会に関する書類で永久保存の必要のないもの
(3) 予算及び決算に関する書類で永久保存の必要のないもの
(4) その他10年及び7年保存を必要とする書類
第3種に属する文書
(1) 諸報告及び統計資料
(2) 台帳登録を終った書類
(3) 職員の出張命令簿、出勤簿及び日誌の類
(4) その他5年保存を必要とする書類
第4種に属する文書
第1種、第2種及び第3種に属しない書類
(引継ぎ)
第39条 主務課等の長は、処理済み文書の引継ぎをしようとするときは、文書管理システムにより移管対象文書リストを作成し、当該文書に添えて、総務課長に提出する。この場合において、保存箱に収納した文書の引き継ぎは、保存箱に入れたまま行うことができる。
2 事務処理上特に必要な文書は、前項の規定にかかわらず、その必要とする期間を限り、主務課等の長が保管することができる。
(文書の保存)
第40条 保存文書は、総務課長の定めるところにより整理し、書庫に保存しなければならない。
(書庫)
第41条 書庫は総務課長が管理し、出入りについては総務課長の指示に従わなければならない。
(職員の閲覧)
第42条 保存文書を閲覧しようとする職員は総務課長の承認を得て、その定められた場所で閲覧しなければならない。
2 閲覧文書は、いかなる理由があっても、他人への貸与、抜き取り、書き込み、取り替え、差し替え等をしてはならない。
(文書の廃棄)
第43条 総務課長は、毎年保存期間を満了した保存文書を調査し、廃棄文書目録(第10号様式)を作成し、主務課等の長に合議し、副町長の決裁を得て廃棄しなければならない。この場合においては、焼却、裁断等により他に悪用されないよう処分しなければならない。
2 保存期間の満了した文書であっても主務課等の長の請求があるときは、なお期間を限り保存しなければならない。
附 則
この訓令は、昭和40年5月1日から施行する。
附 則(平成9年12月18日訓令第2号)
この訓令は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成13年12月20日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 旧規程に定める様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附 則(平成20年3月24日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの訓令の施行前にされた処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月1日訓令第1号)
この訓令は、令和4年3月1日から施行する。
附 則(令和6年2月8日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
課等の名称 | 略字 |
総務課 | 大総 |
防災安全課 | 大防 |
企画財政課 | 大企 |
町民課 | 大町 |
税務課 | 大税 |
協働推進課 | 大協 |
福祉課 | 大福 |
子育て健康課 | 大子 |
生活環境課 | 大生 |
地域振興課 | 大地 |
都市整備課 | 大都 |