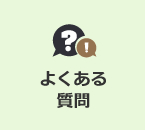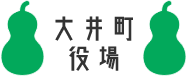令和7年度 全国学力・学習状況調査の結果分析について
1 実施状況
・実 施 日 :令和7年4月17日(木曜日)
・対象校(学年):小学校(6年生対象)3校、中学校(3年生対象)1校
・参 加 人 数 :小学校102人、中学校144人、計246人
2 本調査の概要
本調査は、幅広く児童生徒の学力や学習状況等について把握・分析することを目的としており、今年度は「教科に関する調査(国語、算数・数学、理科)」と「質問調査」が実施されました。
教科に関する調査では、学習指導要領で育成を目指す、知識及び技能や思考力、判断力、表現力等を問う問題が出題され、「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善のメッセージが発信されました。なお、国語、算数・数学及び小学校理科は、冊子を用いた筆記方式で実施され、中学校理科は、生徒が活用するICT端末等を用いた、文部科学省CBT(Computer Based Testing)システムによるオンライン方式で実施されました。
質問調査では、学習意欲、学習方法、学習環境、生活の諸側面等に関する内容について問われ、児童生徒の活用するICT端末等を用いたオンライン方式で実施されました。
3 調査結果の全体的な傾向
(1) 教科に関する調査
☆県の平均正答率との比較について
◎小学校の国語・理科、中学校の国語・理科 … ほぼ同程度(±5%以内)
◎小学校の算数、中学校の数学 … やや低い(-10%以内)
☆国語について
国語では、漢字や語句の意味に関する基本的な知識の定着がみられました。また、文学的な文章においては登場人物の設定を正確に捉える点に、説明的な文章においては時間的な順序や事柄の順序などを考えながら内容の大体を捉える点に成果がみられました。一方、【話すこと・聞くこと】の領域において、話し方の工夫を捉えたり、聞く内容を整理したり関係付けたりする点に課題がみられました。学習場面において、目的や意図を明確にするとともに、相手意識を高め、児童生徒の主体性のある学びになるよう授業改善に努めていきます。
☆算数・数学について
算数・数学では、【数と計算(式)】の領域において、計算に関する基本的な技能の定着がみられるものの、その計算過程を数学的な表現を用いて説明する点に課題がみられました。基本的な知識及び技能の確実な定着を図るとともに、単元や学年をこえた知識及び技能のつながりを意識した系統的な指導に努めていきます。【図形】の領域において、定義を基にした図形の理解や複数の構成要素を関連付けてみる力に課題がみられました。授業において、着目している図形の構成要素を共有したり、明確に示したりするなどして、数学的な見方・考え方を働かせる授業実践に努めていきます。
☆理科について
理科では、実験において条件を整理しながら方法を考え、結果から得られた数値を根拠にして考察する点に成果がみられました。引き続き、観察や実験による複数の結果を比較したり、多面的に考察したりする学習過程を大切にしていきます。一方、【エネルギー】の領域において、乾電池の直列つなぎに関する理解や、電流・電圧、抵抗、熱量に関する理解に課題がみられました。実際に操作したり計測して数値化したりする活動をとおして、実感を伴った理解を得られるよう授業改善に努めていきます。また、授業の中で知識がつながる瞬間を児童生徒自身が実感できるように工夫し、概念的な理解をめざしていきます。
(2) 質問調査
☆考えを工夫して発表することについて
小・中学生ともに、肯定的回答の割合が県や全国と比較して高い傾向にありました。自分の考えを発表する場面において、内容がうまく伝わるように、資料や文章、話の組立てなどを工夫している様子が伺えます。発表に至るまでの過程を重視した学習活動が実施できている成果だと考えます。引き続き、発表する目的を明確にする中で、相手意識を大切にした指導に取り組んでいきます。
☆仲間と協力して学習することについて
小・中学生ともに、9割程度の児童生徒が肯定的に捉えていました。授業において、ペアやグループなど協働的に学ぶ場面を積極的に取り入れている成果だと考えます。また、道徳教育の充実により、相手の意見や立場を尊重した姿勢が育まれている成果だと考えます。昨今、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実が求められていることから、引き続き、「主体的・対話的で深い学び」の視点による授業改善に努めていきます。
☆道徳の授業における学び方について
小・中学生ともに、9割程度の児童生徒が肯定的に捉えていました。自分の考えを深めたり、学級やグループで話し合ったりする活動に取り組む様子が伺えます。日頃の教育活動において、道徳性の育成に努めるとともに、講師を招聘した授業研究会をとおして、児童生徒の問いを大切にした授業づくりに取り組んできた成果だと考えます。引き続き、「考え、議論する道徳」の実現へ向けて、道徳教育の推進に努めていきます。
☆授業におけるICT機器の活用について
小・中学生ともに、「ほぼ毎日使っている」と回答した割合が県や全国と比較して低い傾向にありました。ICT研修などをとおして、教職員のスキル向上をめざすとともに、児童生徒自らが活用するよさを実感できるような取組を推進していきます。また、1人1台タブレット端末が文房具の一つであるという意識をより高め、積極的に活用し、学習を深めていけるようにしていきます。
☆家庭における学習習慣について
小・中学生ともに、「休日の勉強時間」を問う項目において、「全くしない」と回答した割合が県や全国と比較して高い傾向にありました。また、児童生徒の5割以上が、「1時間より少ない」または「全くしない」と回答する結果となりました。この点を踏まえ、タブレット端末を活用した家庭学習も視野に入れて、そのあり方や取り組み方などを学校または学級の実態に応じて検討する必要があると認識しています。学校と家庭・保護者との連携を図り、学習習慣の確立をめざしていきます。
※結果分析の詳細はこちらからご覧ください。