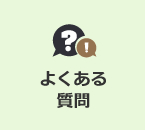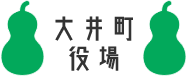乳幼児・児童の各種予防接種
各種予防接種
B型肝炎予防接種
B型肝炎予防接種は、平成28年10月1日から定期接種に加わりました。ウイルスに感染すると急性肝炎となり、回復する場合もあれば慢性肝炎となる場合もあります。一部劇症肝炎といって、激しい症状から死に至る場合もあります。
| 対象年齢 | 標準的な接種期間 | 接種回数・間隔 |
|---|---|---|
| 生後1歳未満(1歳の誕生日の前日まで) | 生後2カ月から9カ月に至るまでの期間 | 3回(27日以上の間隔をあけて2回、さらに1回目の接種から139日以上あけて1回) |
ロタウイルス感染症予防接種
ロタ予防接種は令和2年10月1日から定期接種に加わりました。ロタウイルス感染症は、ロタウイルスによって引き起こされる急性の胃腸炎で、乳幼児期にかかりやすく、水のような下痢、吐き気、嘔吐、発熱、腹痛などの症状があります。
| ワクチン名 | 接種時期と回数 |
|---|---|
| ロタリックス(1価) | 出生6週から24週の間に27日以上の間隔をあけて2回 |
| ロタテック(5価) | 出生6週から32週の間に27日以上の間隔をあけて3回 |
- いずれのワクチンも初回接種を出生6週から14週6日までに実施。
- いずれのワクチンもロタウイルスに対する効果と安全性は同等です。
- 接種後1~2週間は腸重積症に注意が必要です。
Hib(ヒブ)感染症予防接種
ヒブ感染症予防接種は、平成25年4月1日から定期接種に加わりました。インフルエンザ菌、特にb型は、中耳炎、副鼻腔炎、気管支炎などの表在性感染症のほか、髄膜炎、敗血症、肺炎など、乳幼児の重篤な感染症の原因となっています。ワクチンの接種回数・間隔は1回目の接種を受ける時期により異なります。
令和6年4月1日より、4種混合ワクチンにヒブ感染症ワクチンを加えた5種混合ワクチンが開始されます。
対象年齢
生後2カ月以上5歳未満
標準的な接種期間
初回接種:生後2カ月から7カ月まで
追加接種:初回終了後7カ月から13カ月までの間隔をあけて接種
| 接種開始年齢 | 接種回数・間隔 |
|---|---|
| 生後2カ月以上7カ月未満 | 初回接種:生後12カ月までに27日以上の間隔をあけて3回 追加接種:初回接種終了後7カ月以上の間隔をあけて1回 |
| 生後7カ月以上12カ月未満 | 初回接種:生後12カ月までに27日以上の間隔をあけて2回 追加接種:初回接種終了後7カ月以上の間隔をあけて1回 |
| 1歳以上5歳未満 | 1回 |
小児用肺炎球菌予防接種
小児用肺炎球菌予防接種は、平成25年4月1日から定期接種に加わりました。肺炎球菌は、細菌による子どもの感染症の二大原因の一つです。この菌は、子どもの多くが鼻の奥に保菌していて、細菌性髄膜炎、菌血症、肺炎、副鼻腔炎といった病気を起こすことがあります。ワクチンの接種回数・間隔は1回目の接種を受ける時期により異なります。
対象年齢
生後2カ月以上5歳未満
標準的な接種期間
初回接種:生後2カ月から7カ月まで
追加接種:生後12カ月から15カ月まで
| 接種開始年齢 | 接種回数・間隔 |
|---|---|
| 生後2カ月以上7カ月未満 | 初回接種:生後12カ月までに27日以上の間隔をあけて3回 追加接種:初回接種終了後60日以上の間隔をあけて生後12カ月以降に1回 標準として生後12カ月から15カ月までに実施 |
| 生後7カ月以上12カ月未満 | 初回接種:生後12カ月までに27日以上の間隔をあけて2回 追加接種:初回接種終了後60日以上の間隔をあけて生後12カ月以降に1回 標準として生後12カ月から15カ月までに実施 |
| 1歳以上2歳未満 | 60日以上の間隔をあけて2回 |
| 2歳以上5歳未満 | 1回 |
5種(4種)混合予防接種
5種混合はジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ及びヒブの予防接種です。令和6年4月1日から、4種混合ワクチンにヒブワクチンを追加した5種混合接種が開始されます。第二期には二種混合(ジフテリア、破傷風)ワクチンを接種します。
ジフテリアは、ジフテリア菌の飛沫感染で起こります。感染は主にのどですが、鼻にも感染します。症状は高熱、のどの痛み、せき、嘔吐などです。
百日せきは、百日せき菌の飛沫感染で起こります。風邪のような症状で始まり、せきがひどくなります。肺炎や脳症などの重い合併症を起こすこともあります。
破傷風は土の中にひそんでいて傷口から人に感染します。傷口から菌が入り体内で増えると、菌の出す毒素のために口が開かなくなったりけいれんをおこしたり、死亡することもあります。
ポリオは小児マヒと呼ばれ、ポリオウイルスに感染すると風邪のような症状を呈し、発熱を認め、頭痛、嘔吐が現れ、マヒをおこし死亡することもあります。
ヒブ感染症はインフルエンザ菌に感染することで発症し、特にb型は、中耳炎、副鼻腔炎、気管支炎などの表在性感染症のほか、髄膜炎、敗血症、肺炎など、乳幼児の重篤な感染症の原因となっています。
| 対象年齢 | 標準的な接種方法 | |
|---|---|---|
| 第1期 (5種混合) |
生後2カ月以上7歳6カ月未満 | 第1期初回:生後2カ月から7カ月に至るまでに開始し、20日から56日までの間隔をあけて3回 第1期追加:初回接種終了後6カ月から18カ月までの間隔を空けて1回 |
| 第2期 (二種混合) |
11歳以上13歳未満 | 1回 |
不活化ポリオ予防接種
平成24年9月1日から生ワクチンの経口接種から不活化ワクチンによる皮下注射に変わりました。三種混合ワクチンを接種している方が対象です。
| 対象年齢 | 標準的な接種期間 | 接種回数・間隔 |
|---|---|---|
| 生後3カ月以上7歳6カ月未満 | 第1期初回:生後3カ月以上12カ月未満 第1期追加:初回終了後12カ月以上18カ月未満 |
第1期初回:20日以上の間隔をあけて3回 第1期追加:初回接種終了後6カ月以上の間隔をあけて1回 |
ポリオの接種回数について
| 過去の接種回数 | 残りの接種回数 |
|---|---|
| 生ポリオまたは不活化ポリオ未接種の方 | 不活化ポリオワクチンを4回(1期3回、1期追加1回) |
| 生ポリオワクチンを1回受けた方 | 不活化ポリオワクチンを3回(1期2回、1期追加1回) |
| 不活化ポリオワクチンを1~3回受けた方 | 合計4回となるように接種 |
| 生ポリオワクチンを2回受けた方 | 接種不要 |
| 不活化ポリオワクチンを4回受けた方 | 接種不要 |
BCG予防接種
結核の予防接種です。日本の結核患者数はかなり減少しましたが、まだ毎年2万人前後の患者が発生していて、大人から子どもに感染することも少なくありません。乳幼児は結核に対する抵抗力が弱く、全身性の結核症にかかったり、結核性髄膜炎になることもあります。
| 対象年齢 | 標準的な接種期間 | 接種回数 |
|---|---|---|
| 生後1歳未満 | 生後5カ月以上8カ月未満 | 1回 |
麻しん風しん(混合)予防接種
麻しん(はしか)は感染力が強く、飛沫・接触だけではなく空気感染もあり、予防接種を受けないと多くの人がかかり流行する可能性があります。主な症状は、発熱、咳、鼻汁、眼球結膜の充血、めやに、発疹です。はしかは、医療が発達した先進国でも発症者の1,000人に一人が死亡する重症の病気で、日本でも平成12年前後の流行で、年間20~30人が死亡しています。
風しんはウイルスの飛沫感染によって起こります。軽い風邪症状から始まり、発疹、発熱、後頭部リンパ節腫脹などの症状が出ます。大人になってからかかると重症になります。また、妊婦が妊娠20週頃までにウイルスに感染すると、先天性の心臓病、白内障、聴力障害、発育発達遅延などの障がいをもった子どもが生まれる可能性が非常に高くなります。
| 対象年齢 | 接種回数 | |
|---|---|---|
| 第1期 | 1歳以上2歳未満 | 1回 |
| 第2期 | 小学校就学前1年間 | 1回 |
水痘予防接種
水痘(みずぼうそう)は、水痘・帯状疱疹ウイルスの直接接触、飛沫感染あるいは空気感染によって感染し、かゆみを伴う帯状疱疹を発症します。通常1週間程度で自然に治癒しますが、まれに脳炎や肺炎、肝機能の異常を伴うことがあります。また、皮膚から細菌が感染して化膿することがあり、敗血症などの重症の細菌感染症を合併することがあります。なお、成人が水痘にかかると小児より重症になりやすい傾向があります。
| 対象年齢 | 標準的な接種期間 | 接種回数 |
|---|---|---|
| 1歳以上3歳未満 | 初回接種:1歳以上1歳3カ月未満の間に1回 追加接種:初回接種後3カ月以上、標準的には6カ月から12カ月までの間隔をあけて1回 |
2回 |
日本脳炎予防接種
日本脳炎は、ヒトからヒトへ感染することはなく、豚などの体内で増えたウイルスが蚊に媒介され感染します。7~10日の潜伏期間の後、高熱、頭痛、嘔吐、意識障害、けいれんなどの症状が出る急性脳炎になることがあります。
| 対象年齢 | 標準的な接種期間 | 接種回数・間隔 | |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 生後6カ月以上7歳6カ月未満 | 1期初回:3歳 1期追加:4歳 |
1期初回:6日以上(標準は6日から28日まで)の間隔をあけて2回 1期追加:初回後6カ月以上(標準は約1年)の間隔をあけて1回 |
| 第2期 | 9歳以上13歳未満 | 9歳 | 1回 |
平成19年4月2日から平成21年10月1日生まれの方は、1期の対象年齢の期間中に規定の回数を接種できなかった場合、2期の対象年齢の期間中に、不足している回数分を公費(無料)で接種できます。
平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの20歳未満の方の追加接種について
平成17年からの勧奨差し控えによって接種機会を逃した方は、次のとおり不足回数分の接種を受けられます。
| 過去の接種回数 | 残りの接種回数 | 接種間隔 |
|---|---|---|
| 未接種の方 | 4回(1期3回、2期1回) | ・1期初回(2回) 6日以上の間隔をあけて2回 ・1期追加(1回) 1期初回終了後、6カ月以上の間隔をあけて1回 ・2期(1回)9歳以上の方が対象 1期追加終了後、5年程度の間隔をあけて1回 |
| 1回接種を受けた方 | 3回(1期2回、2期1回) | 残りの回数をそれぞれ6日以上の間隔をあけて接種 2期に相当する接種は9歳以上の方が対象 |
| 2回接種を受けた方 | 2回(1期1回、2期1回) | 残りの回数をそれぞれ6日以上の間隔をあけて接種 2期に相当する接種は9歳以上の方が対象 |
| 3回接種を受けた方 | 1回(2期1回) | 残りの回数をそれぞれ6日以上の間隔をあけて接種 2期に相当する接種は9歳以上の方が対象 |
第2期の接種は、第1期追加終了後5年程度の間隔をあけることが望ましいとされていますが、医師の判断により第1期追加終了後6日以上の間隔をあければ接種可能です。
接種の前にご確認ください
平成7年4月2日から平成21年10月1日までに生まれたお子さんは、平成17年5月30日から平成22年3月31日までの積極的勧奨が差し控えられている間に接種を受けた際、母子健康手帳予防接種欄の日本脳炎ではなく、その他の予防接種欄に記録されている可能性があります。接種を受ける前に、接種済みでないかをよくご確認ください。
ヒトパピローマウイルス感染症予防接種
ヒトパピローマウイルス(HPV)は、ヒトにとって特殊なウイルスではなく、多くのヒトが感染し、その一部が子宮頸がんなどを発症します。子宮頸がんは国内で年間約11,000人が発症し、約2,900人が死亡すると推定されています。ワクチンでHPV感染を防ぐとともに、子宮頸がん検診によって前がん病変を早期に発見し、治療することで、子宮頸がんの発症や死亡の減少が期待されています。
対象者
小学6年生~高校1年生に相当する年齢の女子
標準的な接種時期 13歳になる年度
接種方法
| ワクチン名 | 接種時期と回数 | 接種回数 |
|---|---|---|
| サーバリックスワクチン(2価) | 初回接種から1カ月後に2回目、初回接種から6カ月後に3回目 (上記期間が確保できない場合) 初回接種から1カ月以上の間隔をおいて2回目、初回接種から5カ月以上かつ2回目接種から2カ月半以上の間隔をおいて3回目 |
3回 |
| ガーダシルワクチン(4価) | 初回接種から2カ月後に2回目、初回接種から6カ月後に3回目 (上記期間が確保できない場合) 初回接種から1カ月以上の間隔をおいて2回目、2回目接種から3カ月以上の間隔をおいて3回目 |
3回 |
| シルガードワクチン(9価) | (1)1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合(接種回数:2回) 初回接種から5カ月以上の間隔をおいて2回目 (2)1回目の接種を15歳になってから受ける場合(接種回数:3回) 初回接種から2カ月後に2回目、初回接種から6カ月後に3回目 (上記期間が確保できない場合) 初回接種から1カ月以上の間隔をおいて2回目、2回目接種から3カ月以上の間隔をおいて3回目 |
2回または3回 |
シルガードワクチンは令和5年4月1日から定期予防接種用ワクチンに追加されました。
9価のHPVワクチンを公費で接種できるようになりました [PDFファイル/791KB]
HPVワクチンの接種機会を逃した方へ
HPVワクチンの安全性や副反応について
HPVワクチンの安全性や副反応などを理解いただくために、接種の前に必ずご確認ください。
小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ 概要版 [PDFファイル/3.36MB]
小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ 詳細版 [PDFファイル/3.95MB]