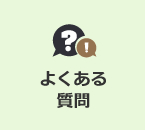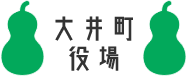医療費が高額になるとき(高額療養費・限度額認定証)
医療費が高額になったとき
国民健康保険(以下、「国保」)の被保険者が1カ月の間に支払った医療費が、一定の額(自己負担限度額)を超えているとき、超えた分の医療費を「高額療養費」として国保が支給します。対象者には、申請不要で診療の2~3カ月後に「高額療養費支給申請書兼請求書」をお送りしますので、申請書が届くのをお待ちください。
なお、事前に限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を申請することで、病院等の窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
申請書が届いたら
申請書に必要事項を記入のうえ、提出いただくと、高額療養費の支給を受けることができます。
高額療養費の手続きが簡素化されました
令和6年12月以降、一度高額療養費を申請いただくと、それ以降高額療養費に該当した場合は、原則として指定いただいた口座へ自動的にお振込みします。対象者には「国民健康保険高額療養費支給決定通知書」を送付します。
例外として自動振込の対象とならない場合
下記の場合は、申請書をお送りしますので町民課に提出してください。
- 自動振込口座の登録手続き期間中に高額療養費が発生した場合(概ね2カ月程度)
- 第三者行為に関するレセプトが高額療養費の計算対象に含まれている場合
- 高額療養費の計算時点において世帯主が死亡している場合
振込先口座を変更する場合
町民課に「高額療養費振込先口座変更届」を提出してください。
自己負担限度額
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
| 所得区分 | 1~3回目 | 4回目以降 (多数回該当)(注2) |
||
|---|---|---|---|---|
| ア | 旧ただし書所得(注1) 901万円超の世帯 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
| イ | 旧ただし書所得 600万円超901万円以下の世帯 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
| ウ | 旧ただし書所得 210万円超600万円以下の世帯 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
| エ | 旧ただし書所得 210万円以下の世帯 |
57,600円 | 44,400円 | |
| オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 | |
同一世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算することができます。
(注1)旧ただし書所得=総所得金額-33万円(国保納税通知書の基準総所得金額と同じ)
(注2)過去1年間に高額療養費の支給を3回以上受けている場合、4回目以降の限度額になります。
70歳以上の方の自己負担限度額(月額)
| 所得区分 | 外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者III 課税所得(注3)690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% ※4回目以降(多数回該当)は、140,100円 |
|
現役並み所得者II |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% ※4回目以降(多数回該当)は、93,000円 |
| 現役並み所得者I 課税所得145万円以上 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% ※4回目以降(多数回該当)は、44,400円 |
| 一般 | 18,000円 ※8月~翌月7月の年間限度額は144,000円 |
57,600円 ※4回目以降(多数回該当)は、44,400円 |
| 低所得者II(注4) | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者I(注5) | 8,000円 | 15,000円 |
8月から12月までは前年の所得を、1月から7月までは前々年の所得を使用します。
(注3)課税所得=総所得金額等-所得控除額-(合計所得38万円以下の16歳未満の国保被保険者数×33万円)-(合計所得38万円以下の16歳から19歳までの国保被保険者数×12万円)
・70歳以上の国保被保険者のうち、最も課税所得が高い方の課税所得を判定に用います。
(注4)同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税の世帯
(注5)同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税で、その各世帯員の所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる世帯(年金所得控除は80万円として計算します)
高額療養費の計算方法
対象となるのは、保険診療で支払った金額のみで、保険のきかない費用(自費診療・差額ベッド代・文書料など)と、食事代は対象外です。
加入者全員が70歳未満の場合
- 1日から末日までの1カ月でかかった金額を、個人ごと、医療機関ごとに合計します。
なお、同じ医療機関でも入院と外来は別計算で、同じ医療機関の入院・外来でも、医科と歯科は別計算です。 - 1で21,000円以上となったもの(処方せんが交付されたときは、病院・診療所分と調剤分を合算します)だけを合算し、自己負担限度額を超えた部分が支給額に加算されます。
加入者全員が70歳以上の場合
- 1日から末日までの1カ月でかかった金額を、個人ごと、医療機関ごとに合計します。
なお、同じ医療機関でも入院と外来は別計算で、同じ医療機関の入院・外来でも、医科と歯科は別計算です。 - 外来分を個人ごとに合算し、自己負担限度額を超えた部分が支給されます。
- なお残る自己負担分と入院分を世帯で合算し、自己負担限度額を超えた部分が支給額に加算されます。
上記以外の場合
- 1日から末日までの1カ月でかかった金額を、個人ごと、医療機関ごとに合計します。
なお、同じ医療機関でも入院と外来は別計算で、同じ医療機関の入院・外来でも、医科と歯科は別計算です。 - 70歳以上の方の外来分を個人ごとに合算し、自己負担限度額を超えた部分が支給されます。
- 70歳以上の方のなお残る自己負担分と入院分を世帯で合算し、自己負担限度額を超えた部分が支給額に加算されます。
- 70歳以上の方のなお残る自己負担分と、1で70歳未満の方の21,000円以上となったもの(処方せんが交付されたときは、病院・診療所分と調剤分を合算します)だけを合算し、自己負担限度額を超えた部分が支給額に加算されます。
限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)
国民健康保険の被保険者が入院や高額な外来受診をする場合、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、入院・外来・調剤時の窓口での支払いが自己負担限度額までになります。「限度額適用認定証」が必要な方は、町民課に申請してください。
なお、マイナ保険証を利用されている方は、医療機関窓口における自己負担額を超える支払いが免除されるため、「限度額適用認定証」は不要です。
また、マイナ保険証を利用されていない70歳以上で「現役並み所得者III」及び「一般」の所得区分の方は、被保険者証兼高齢受給者証または資格確認書で自己負担限度額を確認することができるため、「限度額適用認定証」は不要です。
申請方法
申請先
町民課
申請できる人
世帯主または同世帯の方
・別世帯の方が申請する場合は委任状が必要です。
・国民健康保険税に未納がある方には、発行することができません。完納してから申請してください。
申請に必要なもの
- 限度額適用認定(限度額適用・標準負担額減額認定)申請書 [Wordファイル/44KB] [PDFファイル/105KB]
- 申請者の本人確認書類
- (別世帯の方が申請する場合)委任状 [PDFファイル/145KB]