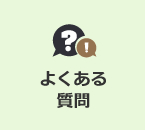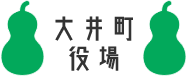裸心版 2024年度
小田町長の裸心版 2024年度
○裸心版とは・・・
このタイトルは、町長としてのさまざまな体験を通じて感じたことを着飾らずに素直に『裸の心で発信』することで、町の進むべき道を皆さんにも考えてもらいたいという思いから「裸心版」としました。
※「羅針盤」は、船や航空機などで方位を知るための器具で、大航海時代の幕を開く重要な航海計器。
※広報おおいに掲載した原稿をWeb用に改稿して掲載しています。2カ月に1度程度の頻度で更新する見込みです。
第5回 2025年 3月 『国旗掲揚』
我が家では、毎年三が日は玄関先に日章旗を掲揚しているが、町内で国の祝日に国旗を掲げている家は、最近ではあまり見かけない気がする。2月11日の「建国記念の日」にも国旗を掲揚したが、この日が「建国記念日」ではなく「建国記念の日」と呼ばれていることに、ふと気が付いた。確かにカレンダーには「建国記念の日」と書かれている。どういうことかと調べてみたら、たった一文字の「の」には、建国記念日をめぐるさまざまな議論と、私には興味深く複雑難解な意味が含まれていた。「建国を祝うことは大切なこと」と考える人々。「史実ではなく、神話を元にした日を祝うのは適切ではない」と考える人々。特に、戦前の「紀元節」との関係や、憲法との兼ね合いが議論の対象になっているとのことである。
「紀元節」は、日本書紀に登場する初代天皇である神武天皇が即位したとされる日を日本の紀元の日として、1872年(明治5年)に制定されたが、戦後1948年(昭和23年)にGHQの意向で廃止された。しかし、その後1951年(昭和26年)頃から紀元節を復活させようという動きが高まり、「建国記念日」設置法案の提出・廃案が実に9回も繰り返され、やっと1966年(昭和41年)に「建国記念の日」が定められた。当初は、「建国記念日」と称して制定しようとしていたが、前述のような意見や議論などから、「建国された日ではなく、建国されたという事象そのものを記念する日」、「建国をしのび、国を愛する心を養う日」という解釈をし、名称に「の」を入れ「建国記念の日」とすることで、ようやく成立したそうだ。なんとも微妙な折衷案だなと感心するところである。
世界各国にも建国を祝う日はあるようだが、多くの国は独立した日や国が成立した日を祝日としている。日本の「建国記念の日」は、独立や憲法制定ではなく「神話に基づく歴史的な由来」に基づいている点が特徴的だと論じられていた。 こうした背景を理解しながら、国の歴史を振り返り、わが国と世界の未来を考える日として、「建国記念の日」の国旗掲揚もある意味で大切なことだと感じた。
そもそも国民の祝日に関する法律第1条には「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。」と記されている。
国旗は国家と国民の象徴であり、そのため国旗に対する敬意は国家と国民への敬意でもあるだろう。
第4回 2024年 11月 『祈り』
11月ともなれば年末年始の足音も聞こえ、冬の訪れを感じる。
和風月名では霜月と呼ばれているが、旧暦の11月はだいたい現在の12月にあたり、霜が降りてくる時期であることからつけられた呼び名と言われている。季節や自然を愛する日本人らしい、風情ある呼び方だと感心する。
この霜月の風物詩の一つに七五三がある。七五三の由来は、平安時代に行われた、3歳の「髪置き」、5歳の「袴着」、7歳の「帯解き」の儀式にあるといわれている。昔は子どもの死亡率が非常に高かったため、このような節目に成長を祝い、子どもの長寿と幸福を祈願した。医療が発達した現代も子どもを思う親心に変わりはなく、七五三というかたちで受け継がれてきたが、現代では、七五三は必ずやらないといけない行事というわけでもないようだ。事情があって行わない、簡略化してお参りのみ行う、袴着や着物姿の記念写真だけは撮るなど、年代によってもその意識はさまざまである。
こんなことは迷信だといえばそれまでだが、いかに時代が変わろうと人として祈る心は大切なものだろう。否、それ故、家族や友人の不治の病や不慮の災難に深い悲しみや絶望と不条理を感じたときは、誰しもおのずと祈りをささげたくなるものではなかろうか。
年末年始などには、どこの寺社仏閣でも多くの参拝者が手を合わせてお祈りしている風景が見られる。人の数だけ夢や希望、願い事があり、改まってお祈りしている姿はとても清々しく思えるが、はて、祈りとは本来はどのようなものだろうか。「困った時の神頼み」という言葉があるが、祈りとは、ただ神仏に状況打開を願ったり、ただ単に願い事を叶えてもらうためだけの行為だけではないように感じる。もちろんそれはそれでいいことではあるが、祈るという行為には人生の苦難に立ち向かい、力強く生きようとしている自分への無意識な心の安寧を感受しつつ、自分の中にいる何かに、または自分自身へ問いかけていく行為のような気がする。
そして、手を合わせ祈るということは、自分以外の大きな存在を認めているということであり、そこに感謝の気持ちが込められ、最高に謙虚な姿ではないかと私は思っている。
第3回 2024年 9月 『脳なんかいらない?』
宮城県庁水産業振興課が配信している、殻付きホヤの捌き方とおいしい食べ方を紹介する動画を偶然見た。ホヤは以前友人に勧められて一度だけ食したことはあったが、ナマコと同様、この類はその見た目も相まって自分の好みではなかった。捌き方を見ていたら、内臓や消化器官、糞を取り除くなど、ホヤの構造がよくわかり、ホヤは動物なのだと改めて認識することができた。
ホヤについて調べてみたら、興味深い情報が多く、時を忘れてしまった。ホヤは貝のようで貝でなく、魚でもない。海のパイナップルとも呼ばれているが、植物でもない。実は海洋動物の系統関係を見ると私たち人間と近い間柄で、脊椎動物と同じ脊索動物に属していることは意外だった。さらに驚いたことは、オタマジャクシのような幼生は、住み家を探して水中を泳ぎ、ここぞという場所を見つけると、でんと動かずを決め、使わなくなった自分の脳までも食べて成長するらしい。何とも不思議である。
なぜそんな生き方をするのか、ホヤの専門家の答えはシンプルだった。「ほとんど脳が必要ないからです。動かないので。」「脳は多くの栄養を必要とする。動かないなら、考えなくていい。脳はなくていい」。それがホヤの生き残り戦略だという。専門家の話はこうも続く。「動けないのではなく、動かないことを選んだ生き物なのだ。研究者としては、そこが面白い」「脳を発達させる戦略で『繁栄』してきた人類から見れば、逆転の発想である」と。
そういえば、子どもの頃、脳だけが溶液の中で永遠に生き続けるという少年SF漫画を読んだ記憶がある。はてさて、生き物とは、いったい何なのだろうか。果たしてこれは進化なのか、退化なのか。
「進化」とは、ある環境で生き延びるのに適した体の構造や生活様式に必要な遺伝子情報を持った生き物が選ばれていく過程であると学んだことがある。それゆえに、ある体の構造がより強調され複雑化していく場合もあれば、逆に目的に合わない構造を捨てて単純化していく場合もあるということか。ヒトの脳は生物学的には最上位に位置付けられているようだ。しかし、ヒトはその脳を持ち合わせたが故に、地球の環境を激変させ、多くの生物を絶滅の危機に追い込んでしまっている。また、大量殺戮兵器の開発など、ヒト自身の繁栄に対して、マイナスと思えるような活動も生み出している。脳のおかげで現在の“繁栄”を勝ち取っているかのようなヒトであるが、脳の無いホヤとどちらが地球上で長く生き延びられるのか、笑い話のようなテーマであるが簡単には予想できないところに不気味な怖さを覚える。
第2回 2024年 7月 『おばあちゃんのバラ』
今年は綺麗な深紅のバラが咲いた。このバラは亡き母が大切に育てていたバラで、家族からは「おばあちゃんのバラ」と呼ばれている。私の雑な手入れにもかかわらず、たくさんの花をつけてくれた。バラを見るたびに剪定はさみを持った楽しげな母の姿が思い起こされる。生きている植物ゆえに、あの頃と今とではバラの姿かたちはだいぶ変わってしまった。母から叱られそうな姿である。それでも、私たち家族は、このバラを「おばあちゃんのバラ」と呼ひ続けていくことだろう。
そんなことを考えていたら、以前読んだ書物に出てきた「テセウスの船」という言葉が頭に浮かんだ。この船は、ギリシャ神話に登場する英雄「テセウス」が怪物ミノタウロスを征伐するために乗り込んだ船で、この功績の大いなる記念として後世へ受け継がれていった。しかし建材の老朽化に伴い、古くなった箇所が次々に新しい部品へと置き換えられていく。こうして、オリジナルの部品が全くない状態となった船は同一の船であろうか。もはや「テセウスの船」とは呼べないのではないか。という物体の「同一性」の保持に焦点を当てた哲学的な問題を提起するパラドックスであると解説されていた。
日本にも似たような考え方は古くから存在し、鴨長明の「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」という方丈記の一節が有名である。「川」としての「存在」はそこにありながら、今そこを流れている水は、時間とともに「その瞬間に流れていた水」ではなくなることを意味しているとのことである。
さて、人間の細胞は数年ごとに全て入れ替わるといわれている。そう考えると生物としての人間の同一性についても考えが及ぶところである。名前は同じだが、肉体的・精神的にいつまでも同じ人間ではなく、日々変化し続けているものだろう。それが進化なのか退化なのかはよく分からないが、過去の自分への呪縛を解くことは、人間として未来への夢に生きるための自己防衛なのではないか都合よく考えてしまう。そうは言っても、一度貼られたレッテルからのイメージチェンジは簡単ではないようだ。
第1回 2024年 5月 『バランス感覚』
高速道路の橋建設現場で、一本の巨大な柱の上部先端から左右に腕を伸ばして行くかのように橋桁を延長し、河川や峡谷の上で巨大な橋脚同士がつながっていく光景を見た方も多いと思う。この工法は通称「ヤジロベエ工法」と呼ばれていて、正式には「片持ち張り出し架設工法」というらしい。この工法は橋脚を建てるスペースが確保できれば工事を進められるため、足元の地形や交通などの影響を受けずに大・中規模の橋を架けることができるそうだ。ちょうど「かかし」が両腕を左右に広げたような姿はまさに「やじろべえ」のようである。この倒れそうで倒れない、絶妙なバランスを保つ「やじろべえ」。子どもの頃、どんぐりと竹ひごで作って遊んだ記憶がある。当時は理科の教材にもなっていたと思うが、今では使われていないようである。それにしても近代的な大規模建築工法にもこんな原理が使われていることに少々興味を感じた。
両者のバランスをとるといえば、弁護士が胸につけているバッジには、外側に正義と自由を表す「ひまわり」が描かれ、中央には公正と平等を追い求めることを表す「天秤ばかり」がデザインされている。また、最高裁判所の大ホールにはギリシャ神話の女神「テミス」をモデルとした「正義像」があり、左手に天秤ばかりを、右手には剣を持っている。剣は正義を実現する強い意志を、天秤ばかりは衡平な判断を表しているとのことである。
不思議に思ったことは、最高裁判所の正義像には目隠しがなく、東京弁護士会の女神像は目隠しをしていることである。女神像が目隠しをしているのは表面的なことにとらわれない法律の公平性と客観性を表し、政治、富、名声などによって決定に影響を及ぼさない意味が込められ、両者に対して公平であること、すなわち「法の下の平等」の法理念を表しているとのことである。ならば正義像が目隠しをしていないことには、すべての事象に対しての真実を完全に見抜けという強い探求心と不変の真理を追究する意思を表しているのだろうか。
さて、法曹界とは違うが、町政運営でもさまざまな施策に公平・公正と平等・正義が求められる。一方を立てれば他方が立たず。公平で平等な施策を立てる時のバランスのとり方にはなにかと心を悩ませるところである。「やじろべえ」は、単なるおもちゃではない。そこには人間として忘れてはいけない何かがあるような気がする。ナントナク。